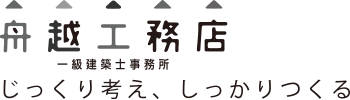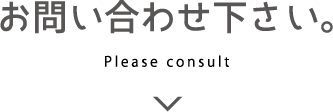舟越工務店ブログ
床暖房のパネルの上に、 床板が張り巡らされてきた。
 床暖房のパネルの上に、
床暖房のパネルの上に、
床板が張り巡らされてきた。
床暖房はガスと電気を熱源とする、
ハイブリット給湯・暖房システムで、
温水温度40度で暖房する、
高効率マットとすることで、
無垢の床板張りとしたのである。
床材は、ロシア唐松厚み15mmで、
板の働き巾は狭めの90mmのものとした。
極力、床暖房による木の収縮を、
考えた選定なのである。
ただ、それでも、木は自然の素材、
多少なりとも動く、収縮することは考えられる、、、
ということをも、想定した上での、選定なのである。
登り軒天の家
エアコンをスッキリ納める
 エアコンを取り付ける。
エアコンを取り付ける。
できるだけ、いい位置取りで、
スッキリと納めたいもの。
壁をふかし、配管を、
壁の中に埋め込むかたちとした。
そうすることで、
いい位置に設置され、
いい位置から、風が出るかたちとなったのである。
同時に建具、片引き戸も、
壁の中に引き込む、
いわゆる、引込戸としたことで、
双方がうまく納まったのである。
+one room project
限定となった位置。
 キッチンの手製の、
キッチンの手製の、
カウンターBOX。
いざという時には、
BOXごと取外せるよう、
床とは、ビス留めのみの、
固定となっているのである。
床は、各部、素材が取り合う部分、、、
杉板、クッションフロア、
そして、床下収納庫。
設置位置は、
おのずと、この位置、
限定となった、のである。
houseリニューアルproject
洗濯機廻りの内容
 部屋の片隅にセットされた、
部屋の片隅にセットされた、
キャスター付の台、、、
スライド式洗濯機置き台なのである。
耐荷重約150kg、
ドラム式の洗濯機にも、
対応できる代物なのである。
その中の床にあるのは、
洗濯排水トラップなのである。
これに、洗濯機の排水ホースを、
接続する。
洗濯機をスライドできるので、
トラップや、洗濯機下の掃除も、
容易にできるのである。
ということで、
洗濯機パンはなし。
当社の定番の、
洗濯機廻りの、内容なのである。
houseリニューアルproject
収納をなくす
 もともとは、深めの収納があった。
もともとは、深めの収納があった。
扉は折戸で、開けると、
前にせり出してくる。
タンス類のレイアウトを考えても、
なかなかこの奥行きが邪魔をする、、、
クロゼットとして使うにしても、
奥行きがありすぎる、、、
収納を撤去した方が、
部屋としても広くなるし、
いろいろな使い様が出来る部屋となるのでは、、、
角部分に柱があったが、
小屋裏を覗くと、
上の屋根荷重を受けていない、
取っても構造的には、
問題ない柱であったのである。
ということで、収納をすっきり、
撤去したのである。
出来上がると、
まさに、跡形もないのである。
広々とした、部屋となったのである。
houseリニューアルproject
採取していた。
 採取していた。
採取していた。
地盤補強工事
HySPEED
天然砕石パイル工法、、、
砕石、なのである。
板の継ぎ目
 床板は、地元産の杉の板。
床板は、地元産の杉の板。
丹波、但馬界隈の杉なのである。
長さは4mなのである。
近頃は、運送屋さんの、
路線便に、長いものが、
不可ということになってきている。
いわゆる、ひとつひとつが、
チャーター便ということになり、
運送代が高くつくことと、
なっているのである。
4mともなると、もちろん、そうなるのだが、
地元の製材所のものであれば、
運送代は、長ものであれ、
なしでいけるのである。
4mあれば、ひとつの部屋内で、
継ぎ目なしで板を張ることが、
結構可能となる、、、
となると、どこで、継ぐかが、
問題になるのである。
部屋とローカは、継ぎ目なしとし、
ドアが閉まった状態のとき、
継ぎ目が隠れるような、
ジョイントの位置とした。
継ぎ目は真っ直ぐにせず、
建具の厚み内で、
一枚ごとに少しずらす、
納めとなっている、のである。
houseリニューアルproject
2018.新年会
 2018.今年も、新年会が、
2018.今年も、新年会が、
京丹波町の、民宿ほそのさんにて、
無事、執り行われた。
新年を迎えて、
家づくりの、職人、、、
プロフェッショナルが集結、
和気あいあいの時を、得たのである。
設計、現場管理、
大工、建材、板金、
左官、畳、塗装、
電気、水道、美装。
普段、現場で顔を、
合わせることも少ない、
職種どうしの方々も、出合う、、、
多岐に渡る、
職種、職能、、、
家づくりの一旦を担う職人、
そして、それらがつながり、
その一連の総合、集結された力によって、
ひとつの家が出来るのである。
1年の、安全、健康をも、誓い合い、乾杯の上、
民宿ほそのさんの、最高の、しゃぶしゃぶに、
舌鼓を打たしていただいた。
あっという間の、実に楽しいひとときで、
あったのである。
皆様、ありがとうございました。
木の間から垣間見えるリビング
 当社モデルハウスの夜の様子。
当社モデルハウスの夜の様子。
木々の間、デッキ越しに、
垣間見えるリビングスペース。
室内、デッキ、植栽、
そして、前面道路という流れ。
多少のレイヤー、
緩衝体を施すことで、
内外双方が生きるのである。
木製ブランコ
 思わず、またもや、
思わず、またもや、
見入った。
いやはや、職業病なのである。
木製のブランコ。
手づくりか、大量生産の、
既製品か。
うまい具合に、
丸太が組み合わさせて、
つくられている。
雨風が当たるので、
焼杉調となっている。
乗り心地も、
なかなか、なのである。
季刊誌 住む。
 ドカッと、5冊は送られてくる、
ドカッと、5冊は送られてくる、
住む。という雑誌
2017.秋号は、
特集 自分たちで、
つくる家。
[集中講座]
木の家を知る。
木の家の
劣化について学ぶ。
いわば、木の家にまつわる、
雑誌なのである。
各号、若干数、
在庫しているのである。
最小限の材、工法の小屋
 見かけた小屋、
見かけた小屋、
塗りコンパネ、半透明の波板、
杭打ちの柱、
細材でつくられた小屋、、、
最小限の材、工法で、
つくられているのである。
強くて優しい工法。

地盤補強工事、
特殊な重機、
長いアームの上を見上げると、
HySPEED 天然砕石パイル工法
50000・・・
ママが選んだ、強く優しい工法、
と、銘打たれているのである。
今は既に、全国で53000棟は、
突破されているよう、、、
昨年施した、
地盤改良工事の様子なのである。
初秋のミニマムハウス
 初秋のミニマムハウス。
初秋のミニマムハウス。
リニューアル改修を施して、
早、6年経過した。
植物の脇を通って、
アプローチする、、、
なかなか、
いい感じなのである。
ミニマムハウス
幕、看板のデザイン
 現場に掲げる、
現場に掲げる、
幕、看板のデザイン。
plan doo.さんにお願いして、
デザインしていただいた。
内容も固まり、
あとは色をどうするか、、、
の思考中の様子。
プリントアウトして、
並べて見てみる、のである。
この見え様も、
なかなか、いい感じなのである。
Rコーナーの部材
 石膏ボード張りの壁面、、、
石膏ボード張りの壁面、、、
壁紙の下地としての使い様なのだが、
出隅の部分、コーナーをRにする、
部材なのである。
サンプルをお預かりした。
断面を見てみる、、、
右上部分がコーナーとなる。
Rは15Rなのである。
大きめのRを見せたい場合は、
使える部材なのである。
天井に仕込む
 杉板張りの天井。
杉板張りの天井。
なにやら、別の木がはめこまれている。
この部分に、スライドコンセントが納まる。
天井面に仕込む予定なのである。
同サイズでつくった、
仮の木なのである。
登り軒天の家
幕開け前の、幕のよう、、、
 建前直前の様子。
建前直前の様子。
ブルーシートで、
基礎もろともカバーされ、、、
下には、柱材等待機の状態なのである。
土台、大引はすでに、
セットされてある、、、
このシートが捲られる瞬間が、
いいのである。
幕開け前の、幕のよう、、、
なのである。
登り軒天の家
土台
 建前まえの様子、、、
建前まえの様子、、、
木にトーメーのビニールが掛けられ、
そのビニールに、土台の文字が、、、
プレカットされた、
ヒノキの土台、大引き類なのである。
いろいろなかたち、
ホゾ加工が施されている。
見てるだけで、
楽しいのである。
登り軒天の家
ガッチリ、ガード
 休み中の現場の様子。
休み中の現場の様子。
ガッチリ、
ガード、するのである。
登り軒天の家
2018.年賀状
 本年も、どうぞ、
本年も、どうぞ、
よろしくお願いいたします。
2018.年賀状、なのである。
土蔵の窓からの緑
 思わず、見入った、
思わず、見入った、
暗い空間から、
一点の窓から、
差し込む光、
見ると、緑が、
目に鮮やかなのである。
切り取られた風景、
かなりの効果的な、
シチュエーションと思われる、、、
秋の頃、、、
土蔵の窓からの緑、なのである。
閑雲居
秋の頃。
 訪れた、秋の頃。
訪れた、秋の頃。
閑雲居の土蔵、
緑が美しい、、、
色付き始めた頃、なのである。
あっという間に、、、
年末となったのである。
閑雲居
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
舟越工務店
年末年始休暇、
12/31~1/7とさせていただきます。
ご迷惑をお掛けしますが、
よろしくお願いいたします。
定番のベントキャップ
 パイプファンや自然換気口などに繋ぐ、
パイプファンや自然換気口などに繋ぐ、
外壁を貫通しての配管の口、
給排気口に取り付けるカバー、
いわゆる、ベントキャップなのである。
今はいろいろなかたち、種類がある。
当社の定番は、これ。
丸型で、ギャラリーが縦にあって、
基本、防虫網はなしのタイプとする、、、
アルミ製の三菱製のものなのである。
不変のデザインなのである。
今回は、外壁の色目に合わせ、
色番号を指定、塗装が施したのである。
登り軒天の家
光の在り様
 窓から、差し込む光。
窓から、差し込む光。
壁面を照らす、
天井も、グラデーションをつけながら、
照らされる、、、
光の在り様が、
より克明に、
わかるようになってきたのである。
自然の光を呼び込み、
室内空間にどう投影させるかが、、、
ひとつのテーマ、なのである。
いわば、その為に成り得た、
かたち、フォルム、在り様、なのである。
登り軒天の家
高低のある、 空間の輪郭
 天井の石膏ボードも張られ、
天井の石膏ボードも張られ、
高低のある、空間の輪郭が、、、
わかるようになってきた、
工事中の室内の様。
2本の梁は、
表わしで見えるつくりとなる、のである。
登り軒天の家
外壁、軒天、窓の納まり
 寄り付く、
寄り付く、
各部位、交点の納まり。
外壁、軒天、窓、、、
うまく納まった、
のである。
着地した感がある、、、
何気なく納まっているように見える、
納まるべきところに、
納まっている、、、
各職人さんの力よって、
なされたのである。
登り軒天の家
掻き落とし
 一晩置き、
一晩置き、
掻き落としとなった。
軒天はすでに、
出来上がっている。
面が平らであることを確認しながら、
少しづつ、、、
塗り面が、
掻き落としされることで、
表情が、まさに、
一変する、、、瞬間なのである。
登り軒天の家
全体が、塗り尽されていく
 山砂掻き落としの、
山砂掻き落としの、
外壁面の塗りが始まった。
先ずは、ベースモルタルの上に、
下塗り材が塗られ、
その上に、追っかけで、
山砂+リシンが塗られるのである。
左官職人さん、4名の、
息のあった、塗りで、
全体が、塗り尽されていく、のである。
登り軒天の家
軒天が塗られた
 先行して、
先行して、
軒天が塗られた、、、
ビニールが張られ、
養生された。
山砂掻き落とし、
冬は、一晩寝かしてから、
掻き落とすのである。
登り軒天の家
山砂
 山砂の様子。
山砂の様子。
山砂掻き落としに用いる、
リシン材と混合され、
塗られるのである。
結構、量がある、のである。
登り軒天の家
-

- フォームからのお問合せ
- お問い合わせフォーム
-

- お電話からのお問合せ
- 0773-27-8739
-

- FAXでのお問合せ
- 0773-27-8030